U-BOYです。
スイスのNagra (ナグラ)より、ネットワークトランスポートが発売されました。
同社のHD DAC XやTube DACは、USB接続を用いることで単体でも最大DSD256のハイレゾ音源に対応しており、PCや汎用サーバーと組み合わせることで、現代のデジタルフォーマットを再生する能力を十分に備えています。
では、なぜあえて今、「Streamer」を世に送り出したのでしょうか。
今回、Nagra StreamerとTube DACを組み合わせて試聴する機会を得ましたので、かんたんな試聴レポートをさせていただきます。

Nagra Streamerについて

まず驚かされるのは、その徹底したミニマリズムです。筐体は同社のポータブルレコーダー「Nagra VII」と全く同じ、アルミニウム削り出しのコンパクトなボディで、実際に持ってみると剛性を感じるずっしりとした質感です。
フロントパネルにはディスプレイも操作ボタンもなく、電源ボタンさえありません。本機が再生プロセスにおいてあくまで「黒子」に徹するトランスポートであるという姿勢がうかがえます。
機能は、高品位なデジタル信号を生成し、DACへ送り出すことに特化されています。Roon Readyに準拠し、Tidal Connect、Spotify Connect、AirPlay 2にも対応。ローカルファイルの再生は背面のUSB-A端子に接続したストレージから可能です。なお、現状Qobuz Connectには非対応です。
USB-A端子はストレージ読み取り用で、オーディオ出力はできません。HD DAC XおよびTube DACにはUSB入力がありますが、それよりも高品位な伝送ができる、光ファイバー接続の「N-Link」を装備しています。
UPnPにも準拠しています。独自のアプリは用意されておらず、汎用のmconnectが推奨アプリとされています。 (基本的にUPnP対応機器はどれでもmconnectで操作できます)
今回は、Roonを使ってデモをしています。
Nagra Tube DACについて

Tube DACは、Nagraのデジタル再生における思想が色濃く反映されたD/Aコンバーターです。
NagraのDAC開発は、かつてPlayback Designs社のアンドレアス・コッチ氏と共同で行われた歴史を持ちます。現在のTube DACはNagra社内のチームによる独自開発ですが、市販のDACチップに依存せず、独自にプログラミングしたFPGA(Field-Programmable Gate Array)を用いて、入力された全てのデジタル信号を一度DSDフォーマットに変換するという手法は、コッチの時代から一貫しています。
現行モデルでは、信号をDSD256(11.2MHz)という高レートに変換することで、信号の過渡特性(トランジェント)を損なう原因となる急峻なデジタルフィルターを不要とし、自然な音楽信号の生成を可能にしています。アナログ出力段には軍用規格の真空管と自社で手巻きした高品質なトランスを採用。デジタル処理の精度と、真空管ならではの有機的な響きを両立させています。
試聴と比較 「Streamerの存在意義」
今回の試聴では、2つの接続方法で音質を比較しました。
- PCとのUSB接続: Ediscreation BACH JP MODEL → (USB) → Nagra Tube DAC
- StreamerとのN-Link接続: Ediscreation BACH JP MODEL → (RJ45) → Nagra Streamer → (N-Link) → Nagra Tube DAC
再生にはRoonを使用し、いずれもEdiscreation BACH JP MODELをRoonサーバーとして使用しました。
USB接続でも体感できる、Tube DACの実力
まず、BACH JP MODELとTube DACをUSBで接続した音を聴きます。これだけでも、一般的なDACとは一線を画す、非常に滑らかで有機的なサウンドです。
よく、Nagraの音は「音楽的」と言われます。例えば同価格帯のdCSやMSBと比べて解像度が突出して高いわけではありません。しかし、弦楽器のウォームな質感や自然な音のたたずまいに共感を得る方が多いのもうなずけます。
デジタル音源にありがちな硬さや刺々しさもありません。特にアコースティック楽器の質感やボーカルの表現は秀逸で、真空管とトランスがもたらす倍音の豊かさ、空間表現も十分広く、Tube DAC単体の実力の高さを十分に感じ取ることができました。
N-Link接続「静寂」と「解放」
次に、接続をNagra StreamerからのN-Linkに切り替えます。
最も大きな変化は、背景の静けさです。S/N比が向上し、音と音の間の暗闇が一段と深くなりました。これは単にノイズフロアが下がったというだけでなく、音楽全体の透明度を引き上げる効果をもたらします。
USB接続では意識下に感じられていたであろう微細なノイズのヴェールが取り払われ、すべての音が何の抵抗もなく空間に解き放たれる感覚です。
N-Link接続は、主に以下の技術的メリットがあります。
- 最適化された独自の伝送方式により、汎用規格であるS/PDIFで発生しやすいクロックの揺らぎ(ジッター)を極限まで抑え込む。
- ガルバニック・アイソレーションにより、上流のデジタルノイズを物理的に遮断する。
Nagra Streamer自体は、一般的な同軸デジタル出力も備えていますが、N-Link接続による、同社のDACとつないで、100%の力を発揮する、Nagra専用トランスポートと考えて良いと思います。
なお、N-Link出力ではDSD256まで対応、同軸デジタル出力もDSD64をDoPで出力することは可能です。
まとめ
Nagra Streamerは、単なる機能追加のための製品ではありません。Nagraが長年培ってきた録音と再生の哲学を、現代のデジタルストリーミング環境で完璧に実現するための、論理的かつ必然的なコンポーネントです。
N-Link接続で音質を確認している時、たまたまお越しになられた常連のお客様が、「これは、とても好みの音だ。良いねぇ」と、しみじみと呟かれました。
その時流れていたのは、ズスケ四重奏団によるモーツァルトの弦楽四重奏。Nagraのシステムは、解像度を誇示するのではなく、弦楽器の温かみやハーモニーの美しさをストレートに表現します。現代ハイエンドの潮流とは異なるかもしれませんが、音楽そのものに深く浸りたいと願う方にとって、この音は抗いがたい魅力を持っています。
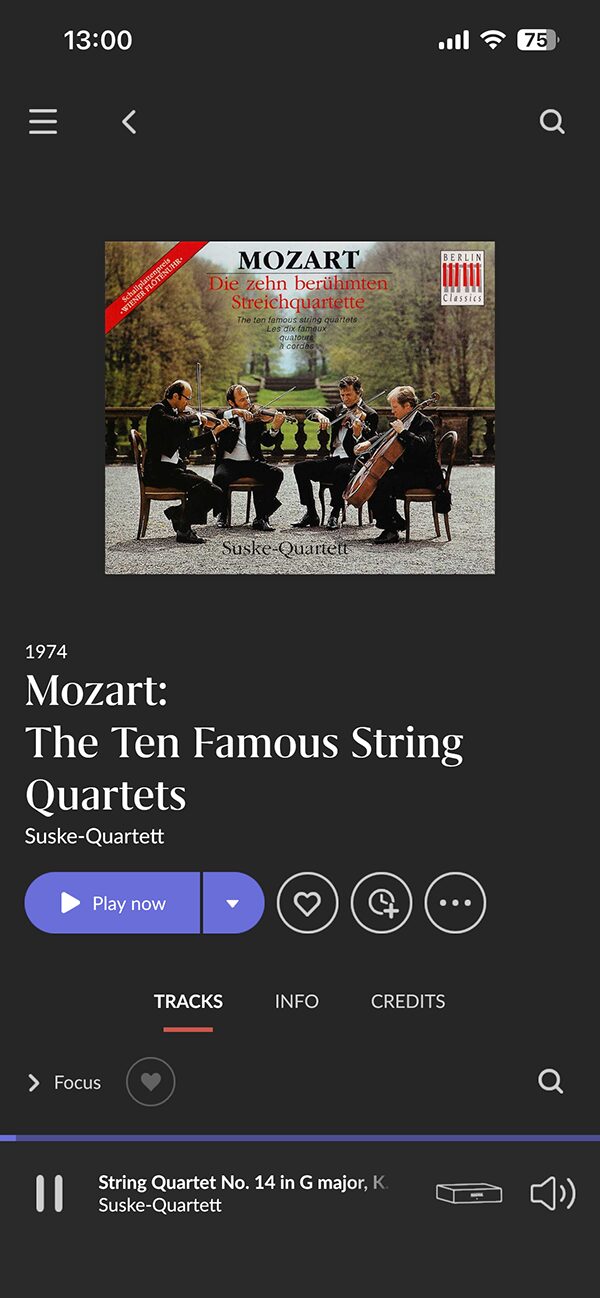
すでにNagraのDACを所有し、その真価を最大限に引き出したいと願うユーザーにとって、Streamerは「待望の答え」と言えます。
製品について興味がある方はお気軽にご相談ください。


 ブログ
ブログ U-AUDIO TOP
U-AUDIO TOP